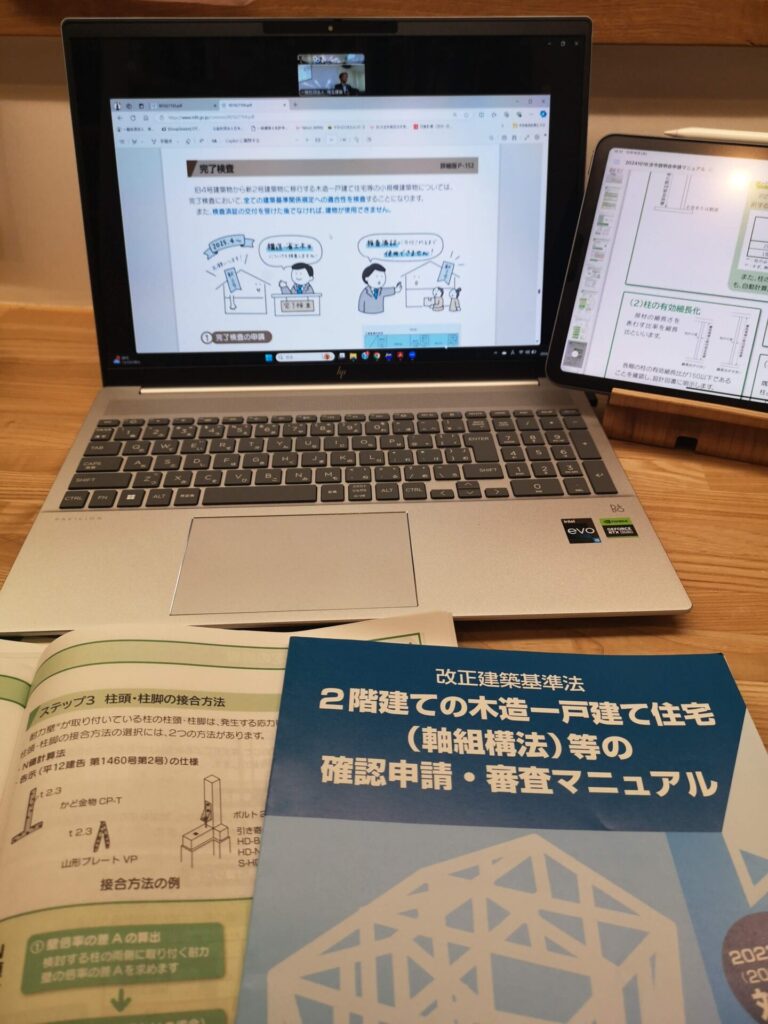【二段ベット工事】 ①仕切るまでの使われ方
House niikuraは2024年で竣工5年が経ちました。
フリースペースを二段ベットで2つの子供部屋に分割するのまでの記録を綴ります。

①仕切るまでの使われ方
新築当初は子供部屋を作らず9畳の真四角なフリースペーを設けました。

ここでは様々な使い方がされてきました。
定番は
●いとこや友人が泊まりに来て布団を並べて皆で寝る…
他の使われ方として、
●ワークショップを開催…

コロナ化で公共施設が借りれないときに、先生が自宅にお越しくださいました。
●子供たちの友達が集まって宿題(^^)

今では男女年齢関係なく遊ぶ姿が懐かしい
●お泊り会では、お化け屋敷も開催(笑)
二つの扉で入口と出口を作りルートを決めて回りました。
親が仕掛ける側になった回も(^^)
●作業部屋に…棚を作ったりと、これがけっこう便利
●一次物置に…ひろげて旅行の準備をしたりと、これもけっこう便利(笑)
こうやって使い方を振り返ってみると、まるで昔の座敷(ざしき)のような使われ方ですね。私の実家にもあるので当たり前に使っていた座敷。
ウィキペディアによると…
座敷とは近現代の一般住宅で、一番よい和室に対して当てられる語。日当たりや風通しが良く、床の間が設けられていることもある。冠婚葬祭などの儀礼や改まった年中行事の場として用いられるほか、客を接待したり、宿泊させることも多い。
出典:ウィキペディア
House niikuraの場合、1Fの玄関横にあり、出入りがしやすく、南に面した場所。形状も真四角なので、多用途に使われるにはもってこいの位置です。
仕切られるまでの5年間、この空間がなかったらできなかったいろいろなことができました。今となっては良い思い出です。
②仕切る?仕切らない?方法は? につづく…
【Process】
1つずつブログで綴っています
①仕切るまでの使われ方
②仕切る?仕切らない?方法は?
③できることはやってみる
④分割工事までの準備
⑤工事当日
⑥監督さんの仕事
⑦工事後の自主施工
⑧家具屋さん見学
⑨初めから仕切るVS後で仕切る
ワークショップ「さかんの磨き体験」
12/1(日)に開催された商工会のイベント「WAKОクリスマスフェスティバル2024」に出展させていただきました。
イベントの中の和光市総合児童センターわぴあ広場での「わこわーく」というお仕事体験のエリアでの出店。
壁などの仕上げ材料「しっくい」のみがき技法をコテや手を使ってアートパネルに仕上げていく「さかんのみがき体験」のワークショップを企画しました。
左官は家の中で、床や壁の仕上げ材料として使われています。
グリットデザインは設計事務所で主に家を造るお仕事をしていて、左官屋さんではありません。
ですが、家を造る過程ではクライアント様と一緒に、左官を始め沢山の材料の中から素材を選んだり、組み合わせを考えたりしていきます。左官は、現場で塗って仕上げていく材料なので、継ぎ目なく仕上がり、人の手で仕上げていくのでとても奥深い仕上がりになります。沢山ある材料の中でも左官はとっても魅力的で奥が深い材料だな〜と私はとても心惹かれるのです。
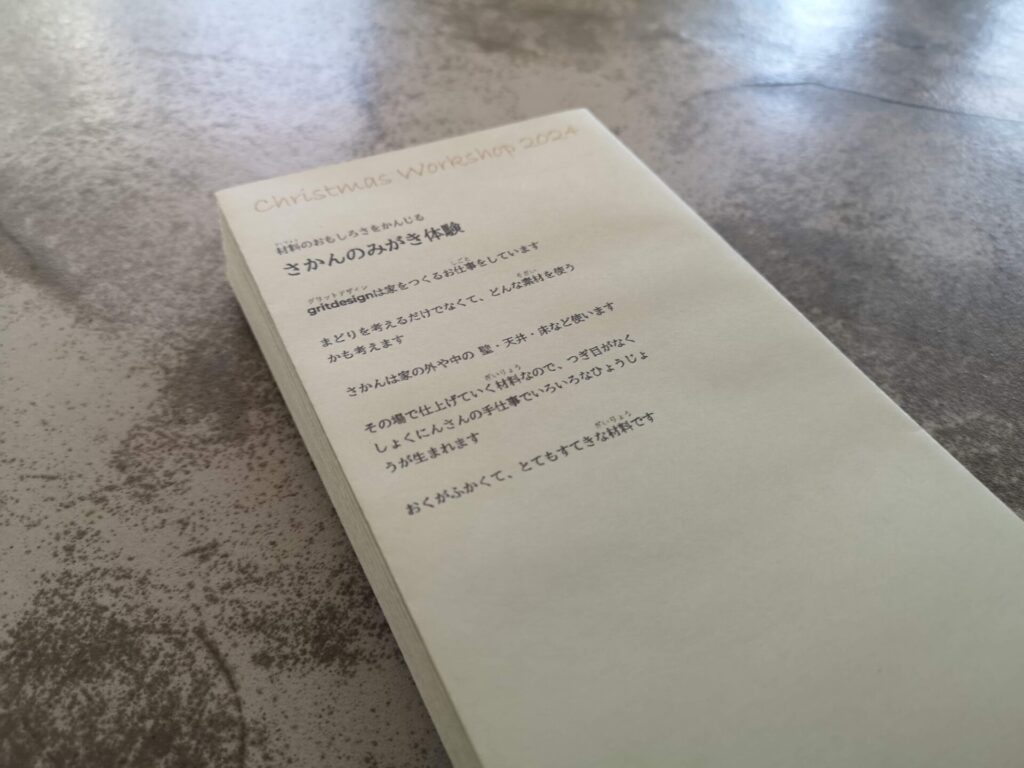
ワークショップの話をいただいた時、グリットデザインをみんなに知っていただきたい。という思いと、地域に向けて何か活動していきたい。という思いが湧いてきました。
子供達も今までに沢山のワークショップに参加させてもらったので、大きくなってきた今、今度は開催する側で参加できたら。という思いと…。
そんな色々な思いが巡って参加をすることにしました。
よりアート感覚ででき、素材の魅力を伝えられて、あぁ。建築って面白いな。といつか思い出してもらえたらと思い、左官をセレクト。その中でも「磨き技法」はかなり難易度が高いのですが、私が体験した際すっかり魅了されてしまい、今回挑戦してみました。
このワークショップ開催のため、改めて左官と沢山向き合いました。
左官職人さんにお話を伺いに行ったり、何度も試してみたり…。

結局下地が一番大事なのだと分かるのに、試行錯誤し2ヶ月くらいかかりました!
下地塗りに手を抜いてはいけない(笑)

共感してくれた友人建築家が下地塗り、そして当日の受付も手伝ってくれました。
子供達が塗りやすいよう制作サイズに。
最後には家に飾ってもらえるように裏に金具をつけてお渡ししました。
当日は大好評で常にキャンセル待ちが出る状況でした。
お施主様もご参加くださり、久しぶりに再会することが出来ました。
ひと通り説明したあと、スタートすると、子供達は躊躇なく塗り進めていく。
慣れないコテで塗る子供達を優しくサポートしたり、じっと側で見守る親御さん方。
どちらも素敵で、もっと左官として仕上げる技法などお伝え出来ることはあったのですが、
言わないほうが良い気がして、私も見守りました。

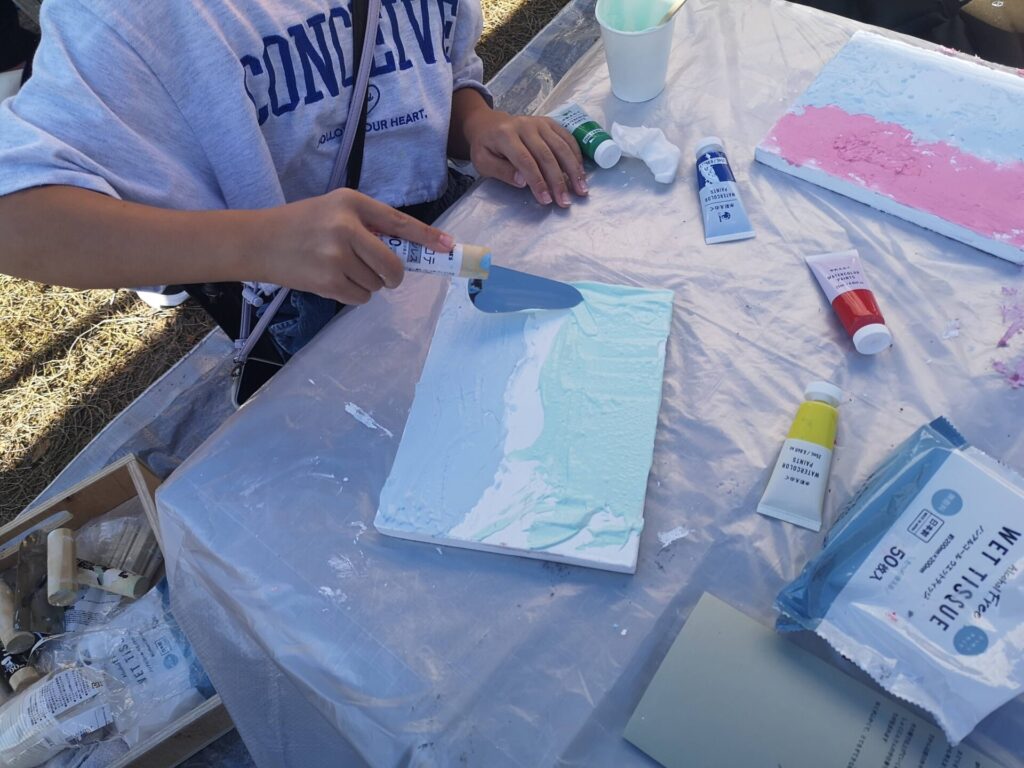

子供達も頑張って店番してくれました(^^)
ラッピング頑張ってくれた次女。
裏で片付けや準備など見えないところで動いてくれた長女。
搬出•搬入を手伝ってくれた主人にも感謝。

皆さんの作品。
とっても個性的。



準備も当日もとっても大変でしたが、予想していたよりも遥かに多くの方に共感していただけて、嬉しく思いました。大人の方もご参加くださり、「私もやってみたい!」と沢山の方からお声掛け頂きました。
また、機会がありましたら、建築や住宅の魅力をお伝え出来るようなワークショップ開催してみたいです。
景観審議会委員
昨年から務めさせていただいている「和光市空家対策協議会委員」に加えて、
都市整備課の方のお声かけで、今期から「景観審議会委員」も務めることになりました。
景観10選にノミネートされている、白子2丁目の「佐和屋」と呼ばれる古民家が、
さまざまな事情から取り壊されることになっているそうです。
すでに景観条例は制定済みのようですが、
「和光市の住民・住環境も変化してきているので、
これを契機に、新しい視点で考え直してみてもいいかと思っている。
ぜひ一緒にいかがですか?」
そんなお誘いのメールが来ました。
私も和光市に移住してまだ7年目。
まだまだ知らない事も多いです。
そんな中、先日は空家対策協議会の件で、リノベについてお話聞きたいと都市整備課の方が自宅までお越しくださいました。
ざっくばらんに話をする中で、北口の土地区画整理・再開発の事業も担当されていると伺いました。
和光市の事、いろいろ教えていただきました。
新旧の住人や街が、お互いを尊重し合い、上手く交わっていけると、お互いに住みやすいのではないかなと思います。
今後の審議会の取り組みとしては、景観計画や景観方針の見直しと、和光市景観10選のアップデート。
たくさんの学びがあって、活発な意見交換ができる場に変えていこうと思ってます。とおっしゃっていましたので、参加させていただき、よき場になれば良いなと思います。
わかっているつもりだけの換気セミナー
換気のオンラインセミナー。
講師は断熱・気密化技術・換気・エコハウスなどの環境のスペシャリスト南雄三さん。
南雄三先生からの提言
「換気を考えるためには、換気だけを考えていてはだめで、断熱・気密・冷暖房を合わせてバランスよく考える必要がある。」
すごく簡単な言葉ですが府に落ちました。
南さんはG1~2レベルの断熱性能だったら第三種換気でも良いと考えていらっしゃることは大きな収穫でした。
第三種換気における熱損失の割合を見ると全体からするとそれほどではないという理由なのだそう。
コストが許せばより良い環境として、熱交換型の第一種換気をご提案した方が良いのかな…でも設備が重装備になるのは本当にいいのだろうか?住宅はメンテナンスも考えてあえてシンプルにつくりたい。
と常々思っていたので、南先生の考え方は嬉しい発見でした。
最後に南さんと参加者の雑談の中で、
「結局どれがいいかは難しいね。」という話が出てきました。
スペシャリストの方々でも絶対の方法があるわけではない。
沢山の手法や設備商品があるので、考え方もいろいろ。選ぶのもそれぞれ。
改めて、「自分軸をしっかり持つ」
南さんおすすめの解説本をすぐに注文。
「建築技術2019年1月
わかっているつもりだけの換気」
ネーミングが面白いです(笑)
カテゴリー:02_work
建築基準法改正
2025年4月から大改正される建築基準法。あと半年のところまで迫ってきました。
本日は埼玉建築士会主催の説明会にオンラインで参加。
gritdesignのお仕事にかかわるところで言いますと、いわゆる「4号建築」と呼ばれている、2F建て小規模木造住宅で、今まで不要だった手続きが増えます。例えば、構造計算や省エネ計算など…。
gritdesignでは、新築住宅では構造計算・省エネ計算ともに行っていますが、基準も変更になるようで、
まだまだ運用方法も完全に決まってはいないようです。このあたりは審査する側、される側皆でやりながら慣れていく感じになりそうです。
確認申請が厳格化されることは、住み手にとっては安心材料が増えるプラス要素ではあると思いますが、審査に一体どれだけ時間や費用がかかるようになるのでしょうか…?
本日のお話や同業の方に話を聞くと、増改築の基準や、詳しい基準はまだまだ不明な点も多いようです。
今年は3年に1度の建築士定期講習受講の年でもありますので、そちらも3月までに受講・試験を受ける予定です。
小さな設計事務所ではありますが、法改正などの情報には敏感に!
こつこつアップデートしていきたいと思います。